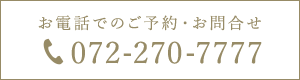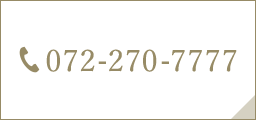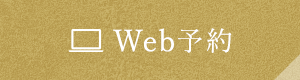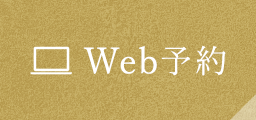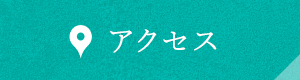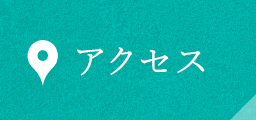【コロナワクチン】遅延型アレルギーの副作用とは?
日本でも新型コロナワクチンのワクチン接種が始まってかなりがたちましたね。
効果(有効性)が高いとされるワクチン接種への期待が高まる一方、やっぱり副反応(副作用)や安全性が気になりますよね。
副反応(副作用)への懸念から、ワクチン接種を躊躇する方もおられるかと思います。
今回はのブログでは、新型コロナウイルスのワクチンについて、医師目線で徹底解説したいと思います。
この記事を読めば、新型コロナウイルスのワクチンについてしっかり理解できると思います。
それでは、どうぞ!
(本稿は日本消化器病学会・認定内科医の中村孝彦医師が執筆しています)

「私は喘息もちなので、コロナの重症化が怖い一人です」
- ファイザー社のコロナワクチン接種状況は?
- コロナのワクチンの有効性は?
- コロナのワクチンの遅延型アレルギーの副作用とは?
- コロナワクチンはうつべきか?様子をみる?
- コロナワクチン接種の実際の手順は?
- ワクチンを接種したら、もう大丈夫?
- 日本での最新接種状況を解説!【速報】
- まとめ
ファイザー社のコロナワクチンの接種状況は?

日本の政府は2021年の上半期に1億2000万回分(6000万人分)のコロナワクチンの提供を受けることでファイザー社(米)と契約しました。
当面は供給量が限られることから、①約400万人の医療従事者→②約3600万人の高齢者→③約820万人の基礎疾患のある人と約200万人の高齢者施設の従業員の順番でコロナワクチンの接種を進める方針となっています。
ここでいう基礎疾患とは、心臓・肺・肝臓・腎臓などが慢性的に悪い方、免疫機能が低い病気を持っている方などです。
コロナのワクチンの有効性は?

日本の政府がワクチンの提供を受ける契約を結んでいるのは、ファイザー社(米)とモデルナ社(米)のmRNAワクチン、それからアストラゼネカ社(英)のウイルスベクター(アデノウイルス)ワクチンの3種類があります。
ファイザー社(米)が開発したワクチンが95%の有効性と発表しているのをはじめとして、モデルナ社(米)とアストラゼネカ社(英)のワクチンもいずれも90%以上の有効率があるとします。
毎年接種するインフルエンザワクチンのワクチンの有効率が20%-60%と報告されていることを考えると新型コロナウイルスのワクチンの有効率は非常に高いといえます。
では、具体的なデータをみていきましょう。
以下、各社のワクチン接種後の中間解析のプレスリリース等をもとに厚生労働省で作成した資料を引用改変しています。
●ファイザー社のコロナワクチンのデータ
ワクチンの2回目接種から7日経過した時点以降で実施した調査で、ワクチンの治験参加者のうち新型コロナウイルスを発症したのは170例で、うち162例がプラセボ(偽薬)群、8例がワクチン接種群でした。
この結果をもって、新型コロナウイルスの発症の予防の有効性が95%としています。
有効性は年齢、性別、人種・民族間で一貫しており、65歳を超える成人では94%を超える有効性が認められたとのことです。
コロナのワクチン接種にあたり重大な副反応(副作用)は認められず、疲労3.8%や頭痛2.0%を認めるのみでした。
●モデルナ社のコロナワクチンのデータ
ワクチンの治験参加者のうち新型コロナウイルスを発症したのは95例で、うち90例がプラセボ(偽薬)群、5例がワクチン接種群でした。
この結果をもって、新型コロナウイルスの発症の予防の有効性が94.5%としています。
コロナのワクチン接種にあたり重大な副反応(副作用)は認められず、2回目接種後に倦怠感(9.7%)、筋肉痛(8.9%)、関節痛(5.2%)、頭痛(4.5%)、痛み(4.1%)を認めるのみでした。
〇アストラゼネカ社のコロナのワクチンのデータ
ワクチンの治験参加者のうち新型コロナウイルスを発症したのは131例で、平均70%の有効性を示しました。
重大な副反応(副作用)は認められなかったとのことです。
コロナのワクチンの遅延型アレルギーの副作用とは?

上記でお示ししたように有効性があるのは間違いなさそうですが、気になるのがやはり安全面、副作用の問題ですよね。
海外の新型コロナワクチン接種者から重度のアナフィラキシーショック反応が出たとの報告もあり、ワクチンの安全面に不安を持たれる方もいるのではないでしょうか。
また、メディアもワクチンの安全性の不安をあおるような風潮であり、少数例の副反応の報告を過剰に宣伝しているきらいがあります。
一般的にワクチンの場合は副作用ではなくて「副反応」という言葉を使います。
ワクチンによる健康の被害は、免疫反応によって起きるため副反応とよびます。
ワクチンの副反応には、一般に①即時型アレルギー、と②遅延型アレルギーの2つがあります。
ワクチンの製剤中の成分がアレルギー反応の原因となるのです。
即時型アレルギーは接種して数日以内に出てくるもので多くは、接種後30分以内に起こることが多く、ひどい場合はアナフィラキシーショックの状態になることもあります。
遅延型アレルギーは、ワクチン接種後、2週間から4週間たってから出てくるもので即時型より頻度が高く、症状は一般に軽度です。
即時型アレルギーのアナフィラキシーは、はじめは、皮膚がかゆい、目まいがするといった症状から始まります。
アナフィラキシーは重症化すると血圧が低下したり息苦しくなったり意識を失うこともあります。
緊急対応が必要になることもあるので、ワクチンは必ず医療機関で接種する必要があります。

米疾病対策センター(CDC)は、ファイザー社のワクチンをアメリカで昨年12月末に接種した189万人の中の21人がアナフィラキシーを起こしたと報告しています。
これは、コロナワクチンのアナフィラキシーの頻度が100万人あたり11.1人の計算になります。
インフルエンザワクチンのアナフィラキシーの頻度が100万人あたり1.3人で、インフルエンザよりは頻度が多いとはいえ、頻度としては十分まれといえるでしょう。
また、アメリカでアナフィラキシーの症状が出た21人の中17人が過去に薬や食べ物に対するアレルギー反応の歴があったと報告されており、基礎疾患やアレルギー歴のない方がアナフィラキシーを過剰に恐れる心配はないといえます。
この21人は年齢は27歳から60歳までで、中央値は40歳、90%が女性で地域的な偏りはなかったとのことです。
アナフィラキシーをおこした85%の人が接種後30分以内に症状が出ました。
この21人で死亡例はなく、21人全員が後遺症なく回復したと報告されています。
アレルギーの原因物質としては、ワクチンに含まれるポリエチレングリコールという物質が指摘されています。
ただし、喘息、じんましんを起こしやすい人、食べ物アレルギー、スギ花粉症、などのある人は注意が必要なので、コロナワクチン接種の際には、その旨を申し出ましょう。
コロナワクチンはうつべきか?様子をみる?

これまで、コロナワクチンについて述べてきましたが、確かにワクチンをうつべきか、打たないべきかは迷うところです。
しかし上述した、ファイザー社(米)、モデルナ社(米)、アストラゼネカ社(英)の治験の結果からワクチンの有効性は明らかです。
また、副反応の項でおしめししたように、コロナワクチンの副反応の発生率はインフルエンザなど従来のワクチンの副反応発生率に比べて極端に高いわけではありません。
すでにイギリスでは、129万人以上、アメリカでは189万人以上が接種しましたが、ワクチン接種と明らかに因果関係のある死亡者はいません。
そもそもワクチンで重篤な健康被害を起こすような副反応の発生率は、通常の内服療法、点滴療法、手術などの医療行為で重大な副作用が起こる可能性より圧倒的に低いことを冷静に判断すべきです。
また、日本でもイギリスなどと同様、新型コロナの変異型ウイルスが増加してくる可能性もあり、未知のウイルスだからこそワクチン接種で集団免疫をつけて防衛する考えもあります。
これまでコロナワクチンのデータについて述べてきましたが、小児・妊婦・高齢者のデータが少ないのは注意すべき点です。
また、20代などの若年者は新型コロナ感染による重症化リスクが、かなり低いと考えられるため、判断が変わる可能性があります。
最終的には「新型コロナ感染による重症化リスク」と「ワクチンによる副反応」を天秤にかけて個々人での判断になります。
コロナワクチン接種の実際の手順は?

日本政府がコロナワクチン購入の正式契約を結んでいるのはファイザー社(米):7200万人分、アストラゼネカ社(英):6000万人分、モデルナ社(米)2500万人分の3社のトータル1億5700万人分とされています。
ワクチン接種の実際の手順は以下のようになるようです。
(ワクチン接種は無料で政府が補償してくれます。)
①自分が住んでいる自治体の発行するコロナワクチン接種券とお知らせが郵送で届きます。
②ワクチン接種できる医療機関や接種会場を選んで、自分で電話やインターネットを用いて予約します。
③ワクチン接種会場に届いた接種券を持って行きます。
会場でアレルギーの問診などで問題なければ医師、看護師にワクチンを接種(筋肉注射)してもらいます。
④後日、日数を空けて2回目のワクチン接種(種類は1回目と同じ)も行い、「接種済証」を受け取ります。
コロナワクチンの予防接種は筋肉注射で行います。
よく比較されるインフルエンザワクチン接種は皮下注射で行われますが、コロナワクチンは皮下組織の内側にある筋肉に薬液を注射します。
ごくまれに発生するアナフィラキシーショックなどに対応するため、ワクチン接種会場には15分以上の経過観察ができる待機場所が確保される予定です。
ただ、ファイザー製ワクチンは-75℃での管理が必要など、集団接種にあたっては管理面での課題があるようです。
コロナワクチンを接種したら、もう大丈夫?

コロナワクチンを接種したら、もうコロナにかからなくなり、収束するのでしょうか。
残念ながら、コロナワクチンを接種した後も少数例ですが、コロナに感染した報告があり、油断はできません。
ワクチン普及後も、これまで通り、マスク、手洗い、三密回避の原則は続けていかなくてはいけません。
また、新型コロナウイルスのワクチンもおそらく、インフルエンザワクチンと同様に毎年接種せざるを得ない可能性があります。
新型コロナウイルスのワクチンにより抗体ができても、インフルエンザ程度の期間しかコロナの免疫が続かない可能性もあります。
世界でも新型コロナウイルスの変異種の報告も相次いでおり、インフルエンザのように毎年違う型が出現するわけではないにしても、おそらく毎年ワクチンを接種せざるを得ない可能性があります。
日本でのコロナワクチンの副作用の実際
日本では、2021年2月14日に特例承認となった新型コロナワクチン「コミナティ筋注(ファイザー社)」を2月17日から先行接種対象者に接種開始しています。
厚生労働省が発表した新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査)によると、表のようなコロナワクチンの副作用が報告されています。

このデータには約2万人が登録し、20代から50代がそれぞれ21-25%、60歳以上が8.7%、男性33.8%女性66.2%でした。
表のように発熱・倦怠感・頭痛といった全身の副反応症状は、2回目接種後の方が発生頻度が高くなっています。
37.5℃以上の発熱は1回目接種後は3.3%に生じるのみでしたが、2回目接種後は35.6%に生じています。発熱する場合は翌日が多く、接種3日目には解熱したと報告されています。
倦怠感は、1回目接種後は23.2%ですが、2回目接種後は、67.3%に増えています。
頭痛も、1回目接種後は21.2%にですが、2回目接種後は、49.0%に増加しています。
接種部位の疼痛は90%を超えるワクチン接種者が自覚し、接種翌日が最も頻度が高く接種3日後には軽快したと報告されています。
また、副反応は高齢者の方が若年者より頻度が少ないと報告されています。
例えば、2回目接種後の37.5℃以上の発熱は、20歳代では半数で報告されているのに対して、50歳代は約3割、70歳代では約1割と減少しています。
コロナワクチンはインフルエンザワクチン(1回接種のみ)の副反応の頻度【発熱(3.1%)、倦怠感(19.0%)、頭痛(14.1%)】と比べると副反応は比較的強く出る印象です。
2回目のコロナワクチン接種の翌日は休養をとるようにとの勧告も出ていますが、いずれにせよ特に2回目の接種翌日は身体に負担のかかる労働や、スポーツ、長時間の車の運転などは避けた方がよいといえます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。

今回のブログではコロナワクチンの副作用と有効性について解説しました。
アメリカのCDC=疾病対策センターも述べているように総合的にはコロナワクチン接種でもたらされる利益は新型コロナウイルス感染症のリスクを上回っていると考えられます。
大阪の堺なかむら総合クリニックでは、新型コロナウイルス検査および、コロナワクチン接種を行っています。お気軽にご相談ください。
↓↓↓

「リスクを過剰に恐れすぎると、コロナワクチンの恩恵を受けられないかもしれません」