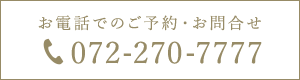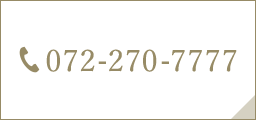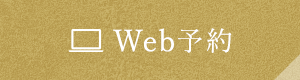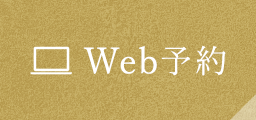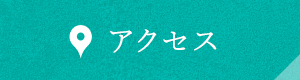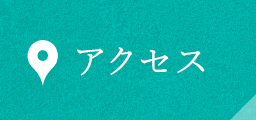【肝臓がんの初期症状をチェック!】
 肝臓がんの初期症状をご存知ですか?
肝臓がんの初期症状をご存知ですか?
肝臓がんというと、どんなイメージをお持ちでしょうか。
お酒飲みの人がなるというイメージでしょうか。
それともC型肝炎やB型肝炎の方がなるというイメージでしょうか。
このブログでは、肝臓がんの初期症状について、医師と一緒に分かりやすくチェックしていきたいと思います。
それでは、早速どうぞ!
(このブログは消化器病専門医の中村孝彦医師が執筆しています)
「最近は、脂肪肝から発生する肝臓がんが注目されているのです!」
- 肝臓がんの初期症状をチェック!
- 肝臓がん・肝硬変の原因はお酒と脂肪肝?
- 肝臓がん・肝硬変の生存率、余命の平均は?
- 肝臓がん・肝硬変の進行速度と検査は?
- 肝臓がん・肝硬変の治療をステージ毎に解説
- まとめ
肝臓がんの初期症状をチェック!

肝臓がんの初期症状としては、全身倦怠感、食欲不振、下半身のむくみがあります。
進行すると、体が黄色くなる黄疸(おうだん)や、腹水(お腹に水が貯まる)による腹部膨満感といった症状が出現してきます。
肝臓がんは、小さなものだと無症状なものもありますが、大きくなると、お腹の外から触知できる腫瘤として認識できたり、もっと大きくなると表面に飛び出し破裂して出血することもあります。
では、このような症状が出る理由は、なぜでしょうか。
肝臓がんのことを考える上で、肝硬変(かんこうへん)とは切っても切れない関係にあるので、肝硬変のお話を先にさせて頂きます。
肝硬変とは、あらゆる慢性肝臓病の終末像であり、肝臓の正常な組織が、機能的な働きを持たない繊維組織に置き換わり、肝臓が硬く変化した状態です。
肝臓が硬く変化するから「肝硬変」という訳ですね。
肝臓を原発として発生する肝臓癌(原発性肝癌といいます)の場合、この肝硬変を背景として癌が出現することがほとんどなのです。
例えるなら、栄養分の足りていない荒れた畑から、悪い作物ができる、といったイメージでしょうか。
これが肝硬変(荒れた畑)と肝臓癌(悪い作物)の関係です。
肝硬変の進行度が進むにつれて、肝臓がんの発生率が上昇することが分かっています。
そのため、肝臓がんが出てくる人は、まず肝硬変の症状である全身倦怠感、食欲不振、下半身の浮腫(ふしゅ)が先に出てくる場合が多いのです。
肝臓がん・肝硬変の原因はお酒と脂肪肝?

肝臓がんの原因の60%がC型肝炎、15%がB型肝炎と、これまではウイルス性肝炎が主な原因でしたが、最近、脂肪肝(正確にはNASH<ナッシュ>といいます)や、アルコール性肝炎からの発癌が増えてきています。
健康診断や人間ドックで指摘された脂肪肝の約10-20%は、NASH<ナッシュ>という肝臓がんの高リスクといわれているので、脂肪肝と言われた方は定期的に血液検査や腹部エコーでチェックする必要があります。
これまで肝臓を原発として発生する肝臓がんのことをお話してきましたが、もう一つ、知っておいた方がよいのは「転移性肝癌」という癌です。
これはその名の通り、他の臓器に原発巣があり、肝臓に転移巣を作ったケースです。
肝臓は、消化管で吸収した栄養を貯蔵する働きがあるため、消化管のほとんどの臓器から肝臓に向かう血管が存在します。
そのため、他の臓器の癌が、この血管を伝って肝臓に転移することが多く、転移性肝癌は原発性肝癌の約20倍ほど存在すると考えられています。
転移性肝癌の原発巣の割合としては、大腸癌が約40%、胃癌が約30%、胆管がんや膵癌が約15%ほどで、ほとんどが消化器系を原発とした癌になります。
そのため、肝臓に腫瘍をみつけたら、原発性肝癌なのか転移性肝癌なのかというのは常に考える必要があり、肝臓がんをみつけたら、胃カメラや大腸カメラも行い、この転移性肝癌の可能性もチェックする必要があります。
肝臓がん・肝硬変の生存率、余命の平均は?
肝臓がんは全体でみると5年生存率は約38%で、ステージごとの5年生存率は以下になります。
ステージ1:63%
ステージ2:40%
ステージ3:14%
ステージ4:3%
しかし、近年、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などの新しい抗がん剤の登場により平均余命は伸びており、今後、5年生存率もこのデータより改善していくことが考えられます。
肝臓がん・肝硬変の進行速度と検査は?

肝硬変は、最初は進行速度はゆっくりで、「代償期(だいしょうき)」とよばれる段階では、食事療法や薬物療法で後戻りできます。
しかし、正常な肝細胞が繊維組織に置き換わっていき、「非代償期(ひだいしょうき)」といわれる時期になると、一気に肝硬変の進行速度が上がります。
肝硬変の進行速度が上がると、肝臓がんの出現の進行速度も上がり、ある時期から、一度に複数の肝臓がんが同時に出現する方も珍しくありません。
肝硬変、肝臓がんの検査の基本は血液検査(採血)と腹部超音波検査(腹部エコー)です。
まず血液検査では、肝硬変の進行度を調べるマーカーとして、肝酵素のAST、ALT、ビリルビン、アルブミンなどの値をチェックします。
肝臓がんの腫瘍マーカーとしては、AFP、PIVKA-Ⅱなどを調べます。
さらに、腹部エコーで肝硬変の進行度がわかるのと同時に、肝臓がんの存在を直接チェックすることができます。
これらの検査で異常を指摘されたときには、CTやMRIといった検査を追加で行うこともあります。
肝臓がん・肝硬変の治療をステージ毎に解説

肝硬変の治療は、その原因によって異なります。
C型肝炎やB型肝炎などのウイルス性肝炎が原因の場合は、ウイルスを排除する直接型抗ウイルス薬(DAAs)で治療を行います。
肝臓の炎症を抑えるためにグリチルリチン製剤やウルソデオキシコール酸といったお薬を使うこともあります。
また、肝硬変によって出てくる腹水に対して利尿薬を使ったり、肝硬変に合併する異常血管である食道静脈瘤に対して内視鏡で出血予防の治療を行ったりします。
一方、肝臓がんの治療はステージごとに異なります。
肝臓がんのステージは癌の個数や大きさ、リンパ節転移の状況などによって決まります。
肝臓がんの治療は肝硬変の進行度(肝予備能といいます)によっても異なります。
肝硬変が末期の状態だと肝移植しか選択肢がなくなります。
肝硬変の進行度が軽度、中等度の段階では、手術や焼灼療法、塞栓療法などを組み合わて治療を行います。
一般的に「抗がん剤」というとステージの進んだ癌というイメージがあると思いますが、肝臓がんの場合は、たとえステージがあまり進んでいなかったとしても抗がん剤を使う場合があるというのは、他の癌と違うところです。
【 まとめ 】
いかがでしたでしょうか。

今回のブログでは肝臓がんについて解説しました。
大阪の堺なかむら総合クリニックでは、超音波検査をつかった肝臓がん早期発見に積極的に取り組んでいます。
健康診断や人間ドックなどで脂肪肝と言われたり、お酒をよく飲む方は定期的に血液検査と腹部エコーでのチェックが必要です。
指摘されたり、気になっている方はぜひお気軽にご相談ください。
肝臓がんのことを詳しくなかった方にとってこのブログが参考になれば幸いです。
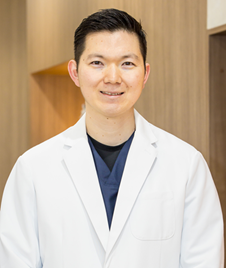 「脂肪肝と言われた方はお気軽にご相談を」
「脂肪肝と言われた方はお気軽にご相談を」